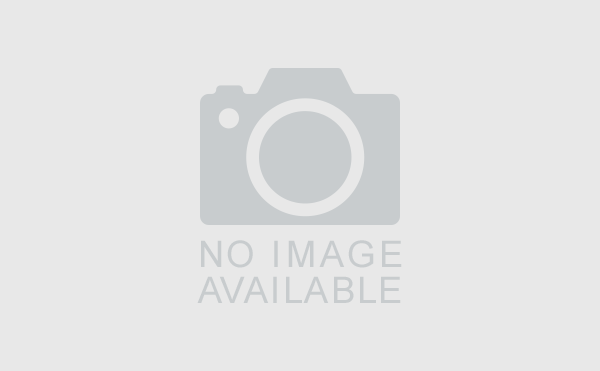精衛海を填む(令和6年6月)
精 衛 海 を 填 む(せいえいうみをうずむ)
令和6年6月 若葉会御講
今月は小鳥が海を埋(う)めよう(填(うず)めよう)と努力した話をします。この話は中国の「山海経(さんがいきよう)」の中に掲載されています。
中国の伝説上の帝(てい)王(おう)に、「神農(しんのう)」という神がいました。形は人間の体に牛の顔をした神です。ある時、天から粟(あわ)が降ってきたので、神農は土地を耕して粟を植えました。また、斧(おの)や鍬(くわ)や鋤(すき)を最初に作ったのも神農とされています。その道具を使って原野を開墾(かいこん)し、五穀(ごこく)(米、麦、粟(あわ)、豆、稗(ひえ))を収穫しました。また百草(ひやくそう)を舐めてどの草が薬になるのか、どの草が毒になるのかを調べました。つまり、草を少し噛(か)んでその結果、体が温かくなる、寒くなるなどの効能や、また病に効くとか、毒の有無などを実験したのです。そのため神農の体は玉のように透き通っていて、五臓(ごぞう)(心臓・肝臓・肺臓・脾(ひ)臓(ぞう)・腎臓)がよく見えていて、解毒作用が自分でできたと伝えられています。世界で最初の医者であり、最初に農業を起こした人であることから、農業の神様ということで「神農」と呼ばれました。
神農は人びとに尊敬されていました。中国湖(こ)北(ほく)省(しよう)には神(しん)農(のう)架(か)という伝説もあります。これはある病人を救うために高山に命懸けで登り、ついに岩壁の頂上の薬草を取って病人を救った時に使った木の柱の架子(かし)(骨組み)のことです。また、神農は火と夏を司(つかさど)る神として炎帝(えんてい)や太(たい)陽(よう)神(しん)とも呼ばれています。
この炎帝の末(すえ)娘(むすめ)に娃(あい)という女の子がいました。この子はとても水遊びが好きで、いつも東の海で水遊びを楽しんでいました。泳ぎもとても得意だったので、炎帝も心配することなく、好きなように遊ばせていましたが、ある晴れた日のこと、急に強い風が吹いて高波が起こり、娃(あい)は一瞬のうちに波にのまれ、溺れ死んでしまいました。魚のように泳いでいた愛(まな)娘(むすめ)を失い、炎帝は太陽の光が薄暗くなるほど悲しみました。その後、娃の魂は精衛(せいえい)という小鳥に生まれ変わりました。この鳥の頭には花の紋様があり、くちばしは白く、細長い足は赤く、尾は長く全体的にきれいな色をしていました。
さて、この鳥には毎日休むことなく繰り返し行なう不思議な行動がありました。それは西の山へ飛んで行って、小枝や小石を口にくわえ、東の海の海に落とすというもので、毎日何回も往復します。日々、何か月も何年も同じ行動を繰り返し行ないました。どうしてこのようなことを続けるのでしょうか?
それは前世において自分を飲み込んだ、東の海を埋める為に行なっているのでした。広大な海を小石や小枝で埋めることはできませんし、不可能なことでしょう。しかし、困難であろうと無理と思われることでも、あきらめず目的を達成するまでは少しも休まず行ない続けるという姿はとても素晴らしく尊いことです。
中国ではこの鳥を何事もあきらめずに行なうという敢(かん)闘(とう)精(せい)神(しん)の代表として挙げられています。また、「精衛々々(せいえいせいえい)」と鳴くので人々は精衛鳥(せいえいちよう)と言いますが、別の名前を前世が炎帝の娘であったことから帝(てい)女(じよ)雀(じやく)とも呼びます。また、志をやり通すという意味で志鳥(しちよう)とも呼ばれています。
私たちはつい、出来るか出来ないか頭で考えて、たし算かけ算でこれなら何日かかる、何年でできると答えを出そうとします。しかし、精衛鳥のやっていることは計算できないことです。だから普通であれば、やっても無理なことだと、やる前からあきらめてしまうでしょう。しかし、どんな大きな山や大海も最初は一粒の土、一滴の水によりはじまるのです。日蓮大聖人様は『唱法華題目抄(しようほつけだいもくしよう)』という御(ご)書(しよ)に、「一(いつ)滴(てき)の水漸々(ぜんぜん)に流れて大海となり、一(いち)塵(じん)積もりて須(しゆ)弥(み)山(せん)となるが如く」と仰せになっています。一滴一滴の積み重ねが大海となり、1つ1つの塵(ちり)の積み重ねが仏教の話の中に出てくる須弥山のような高山になると仰せになられています。皆さんは、本当かな、何万年何億年かかるだろう、計算できないなぁ、と思うことでしょう。しかし、例えば1粒の米粒は植えると1本の稲穂になります。1本の稲穂から50粒の米ができるとしたら、1年目には50粒、50粒の米から2年目には2500粒、これはお茶碗1杯分のごはんに相当します。そして3年目には、125,000粒となり、お茶碗50杯分の米の量になります。
これは計算上のおおよその数なので、実際にそうではないかもしれませんが、とても大きな数になります。そのほか、色々な果物や野菜の種でも、植えて育てれば後に立派な実を成らせます。だからこそ、たった1粒の米であっても残したり粗末にしてはいけません。ある本には、日本人が食べ残す残飯でアフリカの子供たちが数十万人も飢えから救われるそうです。家庭や食堂などで全部きれいに食べられているお皿の方が少ない位です。しかし、野菜も肉も、畑や牧場で何か月も農家の方によって育てられたもので、牛や魚の生命をいただいているのです。だから食べ残して捨てたりしたら、それは本当にもったいないことなのです。ですから、好き嫌いをして家庭での御飯や、学校の給食を残すことがないようになりましょう。
そして、時間にも同じことが言えます。特に皆さんのような少年時代、青年時代の1時間、1日24時間、1ヶ月、半年、1年365日は実に尊い大切な時間です。それは未来の立派な自分自身を築いて行く為に必要な時間だからです。皆さんも精衛鳥のように目標、目的に向かってあきらめず、結果ばかりを気にせず、毎日コツコツと努力精進して、その努力が必ず実を結ぶように、またその努力が2倍3倍にもなって結果を出すことができるように、その尊いお力が具わっている御本尊様に真剣にお題目を唱えて行って下さい。
まずは朝夕の勤行を毎日できるように、生活のリズムを調えてみて下さい。更に、いきなり毎日1時間の唱題といったら大変かもしれませんから、最初は毎日5分、10分の唱題を続け、そこから20分、30分と徐々に時間を延ばして、毎日継続して行うことができるように心掛けてみましょう。ましてや何か自分にとってつまらないこと、嫌なことがあったとしたら、また何か本当に叶えたいことができたならば、そうした時こそ御本尊様にお題目を唱えて、自分の夢や希望を叶え、色々な問題が解決できるようにしましょう。
これから皆さんには、楽しいこと嬉しいこと共に、嫌なこと辛いことも沢山あると思います。昔のことわざで『艱(かん)難(なん)、汝(なんじ)を玉にす』という言葉があります。これは「皆さんに降りかかってくる難事を一つ一つ乗り越えて行けば、知らず知らずのうちに自分を成長させ、やがては玉のように光り輝く存在になり、自然と皆さんが周りの友だちなどから慕われ、愛され、頼りにされるような立派な人になっていく」というのがその意味となります。ですので、今日はこの『艱難、汝を玉にす』という言葉を覚えて、毎日1回はその言葉を口ずさみ、進んで色々なことに挑戦して、立派な大人に成長できるよう努力精進して行って下さい。